有名な本ですが、Amazon audilbleで初めてその内容を知りました。印象に残った部分を以下に記します。
曖昧を受け入れる。
曖昧さを許容できないと、すべてに説明を求めるようになります。
わかるように説明して欲しいと、簡単に言ってしまいます。
物事はそうはっきりしているものばかりではなく、むしろ曖昧なもののほうが多いと言えます。
曖昧さを飲み込むということも、理解の一種といえます。
NHKは公正で客観的?
NKKは公正で客観的であることを公言しています。
しかし何をもってそう言えるのでしょうか。根拠のない自信と言わざるを得ません。
何かを一つの立場から主張する限り、客観でも公正でもないのです。
常識を雑学と勘違いしている。
常識とは、だれが考えてもそうなるだろう、ということです。
断片的な知識ではありません。常識は雑学ではないのです。
幼稚園児なみの東大生。
ある東大生に教授が質問します。「この二つの頭蓋骨の違いについて述べてください。」
東大生は一分間ほど考え込んで「こちらの方が大きいです。」
教授は思わず「ここは幼稚園じゃないんだぞ。」と言ってしまったそうです。
暗算と視覚的処理。
そろばんをイメージした暗算は、視覚的処理で計算をしていると言えます。
脳の機能不全が生む天才。
ピカソのキュービズムは、意識的に脳の機能の一部を停止させて生み出しているそうです。
反応の速さを生むのは、プロセスのショートカット。
イチローの打撃の反応速度は思考のショートカットが生み出しているかもしれません。
その昔、退学処分は復学が前提だった。
学生闘争の時代以前は、退学しても復学のチャンスが与えられていました。
また退学を命じた側が、退学者のその後の人生設計の補助をすることが多かったそうです。
我慢強さを生む前頭葉。
自己の衝動を抑制する機能が前頭葉に備わっています。
この機能が弱いほど自制心が弱まります。
してはいけないことでも衝動的に実行してしまいます。
近年の研究結果で、昔の小学校低学年程度の我慢強さしか、今の小学校高学年は持っていないそうです。
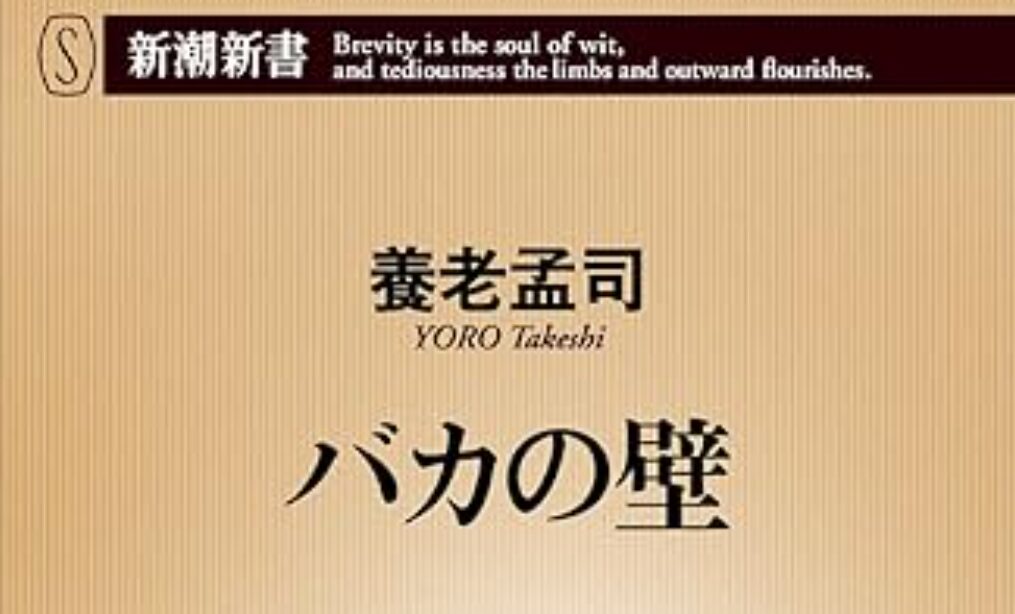

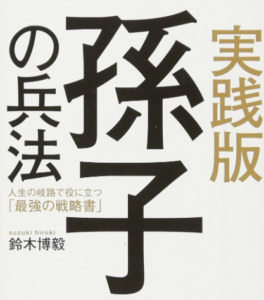
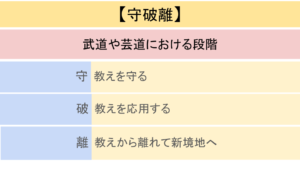
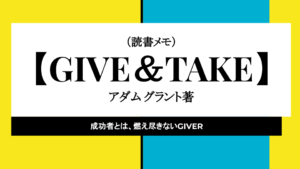

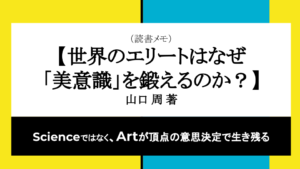
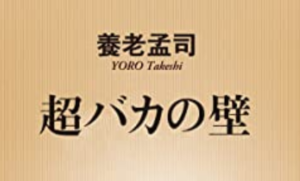

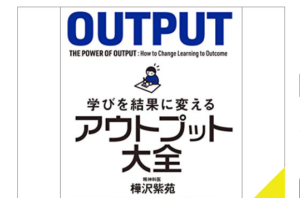
コメント