21『断片集』(紀元前6世紀)
同じ川に二度入ることはできない。万物流転を語る著書です。
著者紹介
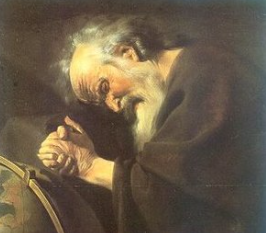
ヘラクレイトス
- Ἡράκλειτος
- Hērakleitos
- 紀元前540年頃 – 紀元前480年頃?
- 古代ギリシアの哲学者、自然哲学者。
- エフェソスで生まれたとされている。
- エペソスの貴族階級に属したことはおそらく間違いがない。
- 民主制を軽蔑し、貴族制の立場を取った。
- 誇り高い性格
- ヘラクレイトスは友人を追放したエペソスの国制を悪しきものとみて、かかわることを拒否した。そしてアルテミス神殿に退いて子供たちとサイコロ遊びに興じた
- 水腫に罹り、医者に症状を伝える際、彼は「嵐を干ばつに変えられるか」と謎かけをし、そのせいで治療を受けられなかったので、自分で治療を試みたが甲斐なく死んだと伝えられる。
- 文章で思想を多く書き残しているためその思想が後世に伝わっている。
万物流転、みな同じ
生きていても死んでいても、起きていても寝ていても、若くても年老いても、これがあれになりあれがそれになるだけのことで、結局は同じことです。単に今の状態が目に映る現実であるだけで、その現実も移ろい繰り返していくことになります。
理、ロゴス
理との調和が人間のあるべき状態です。人間は独立した個ではなくロゴスという理のもとに全体に組み込まれた単位です。
変化と循環
すべてが変化し続け循環することで世界は存在しています。相反するもの同士が戦い変化していく様が世界の和合と循環を成り立たせています。
ワンピース
世界は一つの塊であり、個別に分解しても全体の理解にはつながりません。また二元論で善悪を分別したところで世界をよりよい姿に近づけることはできません。
すべて正しい
全体にかかわるものであればそれらはすべて正しいと言えます。正義や悪があるのではなく、全体の一部や一面がそこに見えているにすぎません。
22『人間知性研究』(17348)
著者紹介

デイヴィッド・ヒューム
- David Hume
- ユリウス暦1711年4月26日〈グレゴリオ暦5月7日〉 – 1776年8月25日
- スコットランドの哲学者。エディンバラ生まれ。
- ロック、バークリー、ベーコン、ホッブズと並ぶ英語圏の代表的な経験論者
- 生得観念を否定し、経験論・懐疑論・自然主義(英語版)哲学に絶大な影響を及ぼした。
- 歴史家、政治思想家、経済思想家、随筆家としても知られ、啓蒙思想家としても名高い。
- 生涯独身を通し、子を一度も残していない。
- イギリス哲学の軸となった経験論の完成者
- 『人間本性論』が主著
- 知識の起源を知覚によって得られる観念にあるとした。
- 人間の知および経験論の限界を示した。
- 『英国史』(The History of England 6巻 1754-1762年に刊行)は、ベストセラーとなり、その後の15年間に多数の版を重ねた。
- この成功に乗じて、それまでの哲学書、例えば大著『人間本性論』(Treatise of Human nature 1739-1740年刊行)を再版して、重要な作品として認められた。
- ヒュームの思想はトーマス・ジェファーソン、ベンジャミン・フランクリンなどのアメリカ建国の父たちにも大きな影響を与えた[1]。
人間学こそ中枢に
人間自身を学問の対象とすべきであり、人間の五感を通じて得られた印象を哲学の基礎に置くべきだと言います。人の本性を明らかにしようとする学問こそが、諸学の基礎のなりうるというのです。
独断からの覚醒
カントが述べるに、ヒュームによって自分は独断というまどろみから覚醒した、とあります。ヒュームいわく、完全な哲学さえも人間の無知を一時的に食い止めるのみである、と。
因果関係は、ただの習慣的連接
因果関係を正確に理解することは不可能です。二重振り子が振りだしの起点がわずかに違うだけで全く異なる動きをして見せるように、同じような原因が全く異なる結果を量産します。それでも因果関係が見えるというなら、それは単なる習慣的連接を因果関係だと誤解しているにすぎません。習慣的連接とは、以前は似たような出来事があった際、その後の結末はこうだった、という経験や知識のことです。
反復することで実在になる
習慣に対する信頼は積み重なり、やがて信念となり、それはたしかな心のよりどころとなります。習慣が繰り返し生み出す結果が、人間にとっての実在です。
習慣は真理ではない
習慣は生きやすくするためのものであり、それ自体が真理ではありません。しかし習慣を実行する人間にとっては真理を手にしたような錯覚をおぼえます。
知覚の束
自己とは知覚の束です。感情や知覚の絶え間ない連なりを自己として認識しているにすぎません。ヒュームに言わせれば、思考は単に思考として存在するだけで、自我の存在を証明するものではありません。
隣接と因果
先行して起こった出来事が、その直後に起こった出来事の原因であるとは限りません。ボタンを押して呼び鈴が鳴ったからといって、ボタンと呼び鈴が無関係である可能性は否定できないのです。しかし出来事が隣接していて、一定の規則性をもって関係性のようなものを見せ続けた場合、私たちはそれを因果関係として見るしかないのです。
本当の無神論者
ヒュームは自身を無神論者ではないと主張します。理由は、神の存在を証明するものが何もない、といっているだけであって、神の存在を否定しているわけではないからです。しかし、神は存在しないというのは神を認識していることになるのである意味で神を信じていることになります。対してヒュームは神を肯定も否定もせず、ただその存在根拠がないといっているので、これこそが完全な無神論かもしれません。
確実と愚か者
確実さを求めるのは愚か者のするこです。人生において確実なのは、やがて終わりがくることだけです。世間一般には確実さを求めるのが一般的でしょうが、確実は非常に高価なモノです。人生において確実さを求めると、人生すべてを費やしても確実のまがい物しか手に入らないでしょう。不安がどうしてもぬぐい切れないはずであり、それは確実なのはやがて死が訪れることだけだからです。
深すぎない哲学
深すぎる哲学にのめりこむことは時に滑稽に映ります。人生において大切なことはそう難解なものではなく、大切なことをいくつか踏まえて行動するくらいでちょうどよいのかもしれません。例えばキケローのように理性に従って生きるのみ、という具合に。
滑稽な哲学
誤った哲学は滑稽ですが、害はありません。宗教の誤りとなると問題は大きくなりますが、哲学は個人の生き方の軸であり、それは他者に直接影響を与えるものではないからです。滑稽と笑われる覚悟さえあるなら、個人的な哲学に没頭するのもいいでしょう。
それでもの経験論
人間の知識を得る能力は感覚によって制限がかかっています。そのため人間は最初から真理に届かないという考え方ができるのですが、それでも感覚を通じて得られる経験をたよりに生きていくしかありません。すべてを疑って生きることは不可能なので、なにかを信じて生きるより仕方がありません。しかし信じたからと言って真理ではないことは忘れないようにすべきです。
23『プラグマティズム』(1907)
著者紹介

ウィリアム・ジェームズ
- William James
- 1842年1月11日 – 1910年8月26日
- アメリカ合衆国の哲学者、心理学者。
- プラグマティストの代表
- 心理学の父である。
- 1875年にアメリカで初の心理学の講義を開始
- 意識の流れの理論を提唱
- 著作は哲学のみならず心理学や生理学など多岐に及んでいる。
- 日本の哲学者、西田幾多郎の「純粋経験論」に示唆を与える
- 夏目漱石も、影響を受けている
意識の流れ
- 心理学の概念のひとつ。
- 米国の心理学者のウィリアム・ジェイムズが1890年代に最初に用いた
- 人はの意識は川の流れのようであり、ビルのような建築物ではない。
- 「人間の意識は静的な部分の配列によって成り立つものではなく、動的なイメージや観念が流れるように連なったものである」とする考え方のことである。
- アンリ・ベルクソンも「持続」という概念を提唱している。
- 文学上の手法としての「意識の流れ」
- この「意識の流れ」の概念は、その後文学の世界に転用され
- 「人間の精神の中に絶え間なく移ろっていく主観的な思考や感覚を、特に注釈を付けることなく記述していく文学上の手法」という文学上の表現の一手法を示す言葉として使用されて文学用語になった。
真理と善
真理は善の一種です。善の中に真理が含まれていて、善の中に人は真理を探すことになります。真理という結晶を探すなら、善という鉱脈をまず探すべきです。
プラグマティズムとは
プラグマティズムとは、原因ではなく結果を目指す態度のことです。またプラグマティズムは結果を求めて過程を重視しないので哲学ではありません。
記述式とマークシート方式
哲学を記述式のテスト形式だとすると、プラグマティズムはマークシート式です。正解を求めてそこへの思考の経路は軽視します。
雑食性が強い
プラグマティズムには好き嫌いが全くといっていいほどありません。プラグマティズムが求めるのは効果のみなので、それが合理論でも経験論でも感覚だろうとオカルトだろうとおかまいなしです。
万人が哲学者
世の中の見方や感じ方それ自体がその人の哲学とも言えます。一般的には気質や性質、性格と言われがちですが。また哲学者の結論は、客観性よりも主観性で導き出されるものです。
二種類の哲学
哲学には相容れない二つのタイプがあり、お互いを見下しています。
経験論
観察と事実に基礎を置く哲学。宿命的で科学的で、悲観的な哲学でもあります。
合理論
永遠の原理を信奉する哲学。抽象的で宗教的で、調和と秩序を信じる楽観的な哲学です。
経験者は語る
富士山を登頂した人が「楽勝だった」と言っても真に受けてはいけません。経験者は真実しか語れないワケではないのですから。
自己保存と攻撃性
何かを真理だと信じる気持ちが強いほど、その真理のようなものに反するものを受け入れることが難しくなります。信じる真理のために他者への攻撃性が高まるのです。
利益と仮説
どんなに不確かな仮説であってもそれが利益を生み出すのであれば信じるに値するというのがプラグマティズムです。
存在と要求
何かが存在する理由は誰かがそれを求めているからです。存在理由とは求められることです。存在は真理を内包しているのであり、存在していること自体が真理の具現です。
24『ファスト&スロー』(2011)
著者紹介
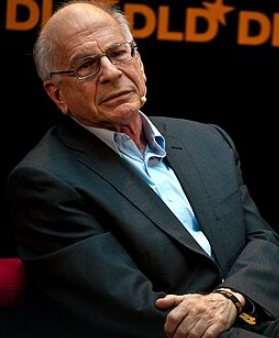
ダニエル・カーネマン
- Daniel Kahneman
- ヘブライ語: דניאל כהנמן
- 1934年3月5日 – 2024年3月27日,90歳没
- イスラエル・アメリカ合衆国の心理学者、行動経済学者。
- 経済学と認知科学を統合した行動ファイナンス理論及びプロスペクト理論で著名。
- ノーベル経済学賞 (2002年)。
- カーネマンは「心理学者はノーベル賞受賞を喜びはするが、私を特別な存在にするとは思わない」と述べている。
プロスペクト理論
- prospect theory
- 1979年、ダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーによって発展した。
- 不確実性下における意思決定モデルの一つ。
- 選択の結果得られる利益もしくは被る損害および、それら確率が既知の状況下において、人がどのような選択をするか記述するモデルである。
ピーク・エンドの法則
- Peak-end rule
- 1999年に発表
- あらゆる経験の快苦の記憶は、ほぼ完全にピーク時と終了時の快苦の度合いで決まるという法則。
ヒューリスティクスとバイアス
- 人が複雑な問題解決等のために何らかの意思決定を行う際、暗黙のうちに用いている簡便な解法や法則
- 経験に基づく為、経験則と同義で扱われる。
- 判断に至る時間は早いが、必ずしもそれが正しいわけではなく
- 判断結果に一定の偏り(バイアス)を含んでいることが多い。
- ヒューリスティックの使用によって生まれている認識上の偏りを、認知バイアスと呼ぶ。
結論を出すな
結論を出すなとは、身もふたもない言い分です。しかしより良い思考を目指すにはそうするより他ありません。なぜなら結論を出すことは思考の完了を意味するからです。特にシステム1に振りまわれないためには結論を避けなければなりません。
システム1
システム1とはいわゆる直感です。超高速で結論を出すシステムで、非常に便利である反面、精度が低く、さらに答えが間違っていてもそうだと納得しづらいという欠陥があります。
最高の時短機能
システム1は超高速で答えを出してくれる、最高の時短思考です。システム1があるからこそ即断が可能になりますが、反面、他の可能性や選択肢を考慮することがなく判断が高いレベルに届きにくいということがあります。例えば良いアイデアがパッと思いつかない場合、あっというまに行き詰ることでしょう。
頭の回転が速い
システム1が頭の回転の速さを担っています。瞬発力を要求されるようなスポーツにおいてシステム1は活躍しますが、プレーの改善についてはシステム2の出番になります。
意見が通るのは
システム1で意見を一番手で述べれば意見が通るかもしれません。しかし2番手で出た意見がシステム2によるものだった場合は勝ちをゆずることになるでしょう。よりよく考えられた意見のほうが通りやすいのは当然で、すばやく意見したシステム1によるものは見劣りしてしまうということになります。しかし、ものは考えようで、システム1の意見が出たからこそ、それが礎となってシステム2の意見がでたとも考えられます。システム1とシステム2の特性を踏まえるなら、まず軽い意見を連発してから、それらをたたき台にしたより良い意見を求めるという手順が最適でしょう。
アイデアの出し方
- アホになる
- 軽々しく意見を連発する
- 出し尽くす
- マジメになる
- 各意見を、分解、合体、反転、変化させてみる。
結論にとびつくマシン
直感は当人の意志とは無関係に作動するシステムで、抑制ができません。直感、つまりシステム1は制御するのではなくそれが出した結論を検証する習慣を身に付けるしかありません。知っていることだけに基づいて、単純に結論に飛びつきます。
弱い根拠で
弱い根拠で極端な予測を披露することは、今のネット社会では普通であり、むしろ推奨されている感すらあります。とにかく結論を先に聞きたいし、それが興味を引く程度には強烈であることが期待される一方で、その根拠となるものは一般的なものでさえあれば関連性の証明は求められず、根拠と予測結果の因果関係すらあやふやでかまわないという風潮です。ほとんどの人は主張の根拠となる事柄の事実確認をしないか、できない状態にあります。
ストーリーさえあれば
主張が真実であるかどうかよりも、単純明快なストーリーであるかが問われます。予測や理論というよりも、世の中に氾濫する主張の多くは断片的情報を線でつないだ一筆書きです。
自信過剰
システム1の欠点は間違うことよりもむしろ自信過剰になるところです。もしシステム1が作動して結論を出しても間違っているかもしれないと自覚できれば特に問題はないでしょう。しかし実際はシステム1でストーリーが完成して結論が生まれた瞬間に正解だと言う自信がうまれ、間違っているという反証を拒んでしまいます。すぐに出た答えが正解であることを願うあまり、その他の答えが正解であるという可能性を自ら切り捨ててしまうのです。
後出し、ご都合主義、自己欺瞞
瞬時に作成されたストーリーのような主張は、のちに的中すれば予想どおりであり、外れればその要因を探し始めたり今後的中する可能性を示唆します。結果をみて主張を変え続けるのが人の一般的な論調です。
見たものが全て
人間の脳は見たものからストーリーを作り上げる力をもっています。限られた情報であっても想像を膨らませてつなぎ合わせる能力に長けています。
システム2
重い腰が上がらない
不確実性下での意思決定
徹底か適当で
長期的な計画を立てるなら、徹底的に綿密な計画にするか、ざっくりとした計画にするかのどちらかが適切です。中途半端な計画がもっとも成果が期待できません。
思考はどこから
人間の思考は突然に発生し、それがどこから来たのかが分かりません。人間は無自覚のまま様々なことを感知して思考して行動を決定しており、その流れを意識的にコントロールできないのです。
思考は感情がほとんど
思考が感情に乱されるというより、思考は感情的なものと言えます。感情に端を発して流れているのが思考であり、感情の流れが思考の流れとも言えます。
意図せぬベンチマーク
意図的に審査基準を設けるのではなく、単に最初に見たものが基準になってしまう場合がありますが、比べているという自覚も薄いために基準が意図せず最初に見たものになっていることにも気づかないことが多いでしょう。極端な場合、最初に見たものに一生縛られて思考し行動する部分があるかもしれません。
整いました
自信がつくというのは成功へのストーリーが頭の中でできたということで、それ自体は喜ばしいことではありますが、実行してみればストーリー通りにことが運ばないということは多々あることでしょう。ストーリーの完成はつぎはぎだらけのでっち上げであることが多く、仮説などと呼べるものでもありません。たとえ実際に成功できたとしても、再現できる保証はどこにもないのです。カンを頼りに作ったストーリーで運よく成功することを期待している精神状態を指して、自信があるというのです。
パラメータを選ぶ
選択が成功につながる確率を高めるなら、選択の基準を2つか3つに絞って機械的に選択することです。人間の経験やカンにたよるとばらつきの大きい低い精度の選択になります。
科学ではない
心理学の中で
人間の知覚を通した体験とその解釈は心理学に関わるものですが、客観的な情報に基づいて真理に近づく科学だと勘違いされることがあります。
原因さがし
システム1が原因を求めています。何が印象に残る出来事があるとその原因を特定したがり、それらしきものを見つけると吟味せずに原因という冠をかぶせます。
ランダムが嫌い
法則性に頼りたいのが人情です。あまりにも運任せな結果論では生きていくうえで不安が大きすぎるからでしょう。こうすれば幸福に近づけるというルールのような法則性を常に求めて人生を送っている面があります。
ビジョナリーカンパニー(笑)
成功した企業の共通点を探しても、それは運が良かった企業の共通点を探したのと大差はありません。成功への確かな原則が存在するというのは幻想であり希望です。ビジョナリーカンパニーで紹介された企業は現在、当時平凡とされた企業と大差のない状態になっています。
それでもストーリー
人を動かすのはそれでもストーリーです。非現実的でも論理展開に飛躍があっても努力と成功の因果関係が証明されていなくても、自分が望む姿に変われるストーリーを思い描けたときに人は思考と行動を変化させます。ストーリーは理論としてではなく、人を変化へと起動させる原動力として読まれるべきです。
気の持ちようと認知
気分の持ちかた一つで人間の認知は変わります。沈んだ気持ちでは最悪に思える出来事でも、幸福感に満たされた状態では大したことには思えないものです。
25『純粋理性批判』(1781)
著者紹介

イマヌエル・カント
- Immanuel Kant
- 1724年4月22日 – 1804年2月12日
- プロイセン王国の哲学者
- ケーニヒスベルク大学の哲学教授
- 『純粋理性批判』、『実践理性批判』、『判断力批判』の三批判書を発表
- 批判哲学を提唱
- 認識論における、いわゆる「コペルニクス的転回」をもたらした。
- 大陸の合理論とイギリスの経験論の哲学を綜合したといわれる
知識と主従関係
新しい仕事を覚えようとする時、人は知識を経験を通して学びます。知識が身について仕事がある程度できるようになると、その後に得た知識は身に付けたスキルのパーツとなります。仕事のスキルはあるレベルに達すると知識との主従が逆転するのであり、初心を忘れるとは自分のスキルが知識の従者であることを忘れることです。
超越論哲学
- 哲学とは「全ての哲学的認識のシステム」
- 超越論的とは、先天的とは異なり「如何にして我々は先天的認識が可能であるのかその可能性と根拠についての問う認識」
- 超越論的な認識とは、われわれが一般に対象を認識する仕方に関する一切の認識を意味する
- 超越的原則とは、制限を踏み越えることを命じるような原則を意味する。
物自体
- 『純粋理性批判』の中で、経験そのものを吟味した際、経験の背後にあり、経験を成立させるために必要な条件として要請したもの。
- 「感覚によって経験されたもの以外は、何も知ることはできない」というヒュームの主張を受けて、カントは「経験を生み出す何か」「物自体」は前提されなければならない
- 「物自体」は経験することができない
- 物自体は認識できず
- 存在するにあたって、我々の主観に依存しない。
- 因果律に従うこともない。
- 「物自体」のような知的な秩序があるかどうかわからない
- その後の経験によって正当化されるであろう。
アプリオリ
- (羅: a priori)
- 「より先のものから」を意味するラテン語表現。
- 中世スコラ学においては「原因・原理から始める演繹的な(推論・議論・認識方法)」という意味で用いられていた
- カント以降は「経験に先立つ先天的・生得的・先験的な(人間の認識条件・認識構造)」という意味で用いられるようになった。
ヌーメノン
- noumenon
- 複数形の「ヌーメナ」(noumena)とは、
- ギリシャ語の「ヌース」(希: νους, nous、精神)に由来する
- 「考えられたもの」「仮想物」を意味する語。
- 「フェノメノン」(phenomenon)や「フェノメナ」(phenomena)、すなわち「現象」と対照を成す語
- プラトンが言うところの「イデア」に相当する。
定言命法
- カント倫理学における根本的な原理
- 無条件に「~せよ」と命じる絶対的命法
- 定言的命令(ていげんてきめいれい)とも言う。
星空と道徳法則
カントの墓碑には星空と道徳法則を讃える言葉が刻まれています。人間は道徳法則に従って幸福を求めるべきだとカントは言います。
手段にするな
人間であることが人間の目的です。決して人間を何かの目的を達成するための手段にしてはなりません。人間が幸福になる権利を何かの代償を与えることで奪ってはなりません。
幸福となるに値する
人間は幸福になろうとする前に、幸福になるに値する人間である必要があります。人間のありようを決定するのはその人間の行為であり、その行為がその人間の値打ちを決めます。幸福になるには、まず幸福になる資格を行為でもって手に入れるべきです。
人間を学ぶ
人がどういうものかを学び、人がどうあるべきかを学ぶことが大切です。また、人間と幸福の関係性や、人間と自由の関係性についても同じです。さらに道徳性と人間のありようについても学ぶ必要があるでしょう。
受動的か、能動的か。
人間は能動的に生きているのでしょうか。それとも受動的でしょうか。生まれる環境は選べないので外的な要因に対しては受動的にならざるを得ませんが、その後どう生きるは能動的に選択することができます。しかし環境的な制約は個人にとって小さいものではなく、将来的に自分がどうなるかはその時の現状から想像するのは難しいでしょう。単純に生まれた時点から時間が経過するなかで、その延長上にしか展望は開けないため、個人の意志で未来を選択することはできないように思われがちです。それでも、個人の持ち味を生かしてそれを駆使して生きていこうとするとき、それまでに持っていたその先の展望が徐々に変わっていくはずです。突然に見える景色が変わることはなくとも、進行方法がわずかにズレただけで進むほどに人生の展望が変化します。個人の意志で選択して生きていくことは、進む方向をずらすことであり、個人が望む幸福に向かって進んでいくことです。
世界観、立ち位置
世界が変わって見えるのは、自分が進む道を行くことで世界の見え方が変わったからです。自分の立ち位置が変わったから見える景色が変わっただけのことで、世界が変わったのではありません。だから個人の世界観とは、単にその人の立ち位置と見ている方向にすぎないのです。
物理の世界、形而上の世界
物質や物理の世界が全てと考えるのか、それとも形而上学の入り込む余地がこの世にあるのか、それは避けられない命題です。いくら物理法則が正しいといってもそれだけでこの世のすべてを説明できるほどには人間の科学は進歩していません。いずれ科学が全てを解明するだろうと考えることが傲慢であるなら、やはりそこに形而上学が入り込む余地が認められます。分からないことや説明できないことに解釈を与えるという意味では、形而上学が日常の多くの部分を支えています。
形而上学(けいじじょうがく)
- 哲学の一分野
- 存在論は「存在とは何か」
- 実在論は「実在とは何か」
- 抽象的な概念を扱う
- 物理的な現象を超えた領域を考察する。
- 存在そのものや宇宙の根本原理を探求する
- 古代ギリシャの哲学者アリストテレスに始まる。
科学
- 《science》
- 事象の研究。
- 認識活動。
- 一定の目的・方法。ルールに基づく。
- その成果としての体系的知識。
- 自然科学・社会科学・人文科学などに分類される。
- 哲学・宗教・芸術などと区別される。
- 広義には学・学問
- 狭義では自然科学だけをさす。
26『おそれとおののき』(1843)
著者紹介
キェルケゴール
- セーレン・オービュ・キェルケゴール
- デンマーク語: Søren Aabye Kierkegaard
- 1813年5月5日 – 1855年11月11日
- デンマークの哲学者、思想家
- 実存主義の創始者
- ヘーゲル学派
- 当時のデンマーク教会に対する痛烈な批判者
実存主義
- 英: existentialism
- 人間の実存を哲学の中心におく
- 現実存在(existentia)の優位を説く
- 存在主義
- 現実存在でない普遍存在との間の差異
- その哲学を実存哲学という。
信仰、情熱。
信仰は自分自身を放棄させ、それを喜びとします。また普遍的なもののために勇気を奮い立たせることで心の安定を得ることができます。
愛して、偉大に。
その人が愛したものの偉大さに応じて、その人は偉大になります。また自分自身を愛した人は自分自身によって偉大になりえ、他人を愛する人はその献身によって偉大になります。
疑うか、信じるか。
人の選択はある意味で、疑うか信じるかの二択と言えます。時に強い信仰は人を狂人に変えますが、それでも信仰は人間の最大の力を引き出すトリガーとなりえます。
求めるべきは、最善か。
最善を求めれば時にすべてを失います。すすんで無力になり信じるもののためにすべてを捨てる覚悟が人を救うことがあります。最善を求めることは、実は最大のリスクを冒すことにつながります。
難行、偉大。
偉大であることが偉大なのではなく、偉大になる道を辿ったところに偉大さの本質があります。運や才能に神頼みのような心では、偉大への道は開けません。
27『名指しと必然性』(1972)
著者紹介
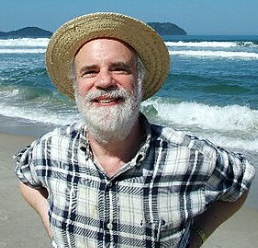
クリプキ
- ソール・アーロン・クリプキ
- Saul Aaron Kripke
- 1940年11月13日 – 2022年9月15日
- ネブラスカ州オマハ生まれ。
- アメリカの哲学者、論理学者。
- プリンストン大学名誉教授。
- ユダヤ人。
- 6歳までに古代ヘブライ語を独学
- 9歳までにシェイクスピアの全集を読み
- 小学校卒業前にデカルトの著作や複雑な数学の問題をマスターするなど、神童と呼ばれていた。
- 高校在学中の17歳の時に自分が発見した様相論理の完全性定理についての論文を書き、翌年に出版した。
- 1958年、高校を卒業し、ハーバード大学に入学。
- 1962年、数学のB.A.を取得し、ハーバード大学を首席で卒業した。
- 後にクリプキは、「大学はすっ飛ばせればよかった。面白い人たちと知り合えたけど、何かを学んだとは言えない。どうせひとりで読んだら全部わかってしまっていたと思う」と語っている。
- ウォーレン・バフェットと面識があり、投資で財を成している。
形而上学の復権
言語分析哲学により、形而上学は葬られたかのようでしたが、クリプキは主流となった言語、唯物論者の欠陥を指摘すつ手段として形而上学を復権させました。
記述と存在
ある人を名前を使わずにその説明、つまり記述だけその名前を言い当てさせることは可能でしょう。たとえその記述のすべてが事実無根であったとしても、世間一般の認知と合致しているのなら記述は特定の存在を指し示すことが可能です。これはつまり、記述の正確性が存在の証明にはならないということであり、不正確な記述がされていても存在は実在であるということです。
自分を記述する
自分自身のことを記述してみたことはあるでしょうか。私は経験がありませんが、恐ろしい気がしてできそうにもありません。自分を客観的に解釈して記述することになりそうですが、そこには自分びいきを無理やり排除してどこか厳しい記述のしかたをしなくてはならないような気がします。他人が自分のことをどうこう言うのも聞きたくないのに、なぜに自分から好き好んで自分のこと記述することがあるのかと思います。しかし、わずかに思うだけですが、そういったしたくもない自己解釈をしてみることで、自分の弱みや強みを理解できて、これから自分にできる最大限のこととは何なのかイメージが湧いてくるかもしれないと考えます。
間違いでも可
記述が精密であろうとなかろうと、指し示す内容を特定することは可能です。言葉の正確さにこだわると、かえってさまざまな誤解を生みかねません。人は思うほど正確に知覚できておらず、また知覚したものをありのままに言葉で表現できるわけでもありません。どんなに客観的で普遍的な表現を心がけても、主観はつきまとうし認知上のバイアスを消し去ることもできません。正しい言葉づかいもそこそこに、正しく伝わっているのかの確認を重視すべきでしょう。
本質、あるがまま。
あるがまま、ということが本質的であるということで、そうでないなら正しくないということになります。言語でどんなにただしく何かを表現したところで、その何かの本質を証明することも否定することもできません。例えていうなら、どんなラベルを貼り付けても中身は変わらないということです。
金、ゴールドの魅力
不変の輝き、それが金、ゴールドの魅力でしょう。輝くものは他にもあるますが、それが永遠のように感じらるものとして金は最高峰なのでしょう。また、不変であるとは他者に影響を受けないということであり、化学反応をことごとく拒否する、かのような性質を併せ持っていることが魅力です。
言語に頼れない
言葉が何かを指し示すことができるのは事実ですが、正確な表現が何かを正確に表現できるとは限りません。物事にはいくつもの側面があり、それらを同時に表現することはできませんし、仮にできたとしても受けての認知バイアスという歪んだレンズも存在するため、言葉で何かを正確に表現することは実質的に不可能に近いものと言えます。
科学という偏見
科学的に現象を分析して理解することは現代社会の常識ですが、科学は自然主義的であり唯物論的な偏見だとも言えます。合理的であるという理解のしかたも、単に一つの尺度においてそうであるにすぎません。科学的に証明されている、という正義の証は、科学が正義そのものであるという偏見に支えられているのです。
『科学革命の構造』(1962)
わずか170ページの論文で24か国語に翻訳されたミリオンセラーの著書。科学辞典の記事を、素人にも読みやすい文章にまとめたもの。
著者紹介

トーマス・クーン
- トーマス・サミュエル・クーン
- Thomas Samuel Kuhn
- 1922年7月18日 – 1996年6月17日
- アメリカ合衆国の哲学者、科学者。
- オハイオ州シンシナティ市のドイツ系ユダヤ人
- ハーバード大学で物理学を専攻
- 1965年7月13日に行われた「批判と知識の成長」と題するシンポジウムにおいて、クーンは徹底的に批判された(後にこのシンポジウムは、「ポパー派によるクーンの袋叩き」と評されている)
- クーンのパラダイム概念は、科学史・科学哲学だけではなく、社会科学や人文科学、果てはビジネス本にまで登場する
- 肺癌で1996年に死亡した。
パラダイムと時代。
世界観、ともいえる時代を支配するような世界の見方を指します。
宗教、世界観。
時代はパラダイムとある意味で同義です。時代が変わるということは、パラダイムがシフトするということで、例えるなら宗教を変えるようなものです。
窮地、変化。
人間は一つのパラダイムの中で思考し行動しますが、そのパラダイムでうまくいかないと感じた時に新しいパラダイムへの移行を開始します。
科学と進歩
進歩という空想
まるで歴史年表のように科学の発展が時系列に並べられることがあるので、あたかも科学が一つの流れをもって進歩しているという認識が広まっている感があります。
科学者とパラダイム
科学者も自分のパラダイムのもとに研究をして新発見や仮説の証明を行うはずですが、うまく行かない時には自身のパラダイムの変換を余儀なくされます。従来の認識を捨てて新しい理解の方法を見つけなければ、科学の進歩はなかったでしょう。
眼鏡のレンズのよう
パラダイムは眼鏡のレンズがのようなもので、付け替えると世界が今までとは違って見えます。しかしパラダイムは眼鏡のレンズ以上に物の見方を変化させうるもので、今まで見ていたものがパラダイムの変換によって全くの別物に変わることもあるでしょう。
パラダイムの性質
パラダイムはその時代に根差すものであり、その時代の事象のほとんどを説明することができますが、逆に言うとそうであるからこそそのパラダイムはその時代のパラダイムたりえるのです。
納得できる間違い
パラダイムは根本的に間違っている可能性があり、大衆が信じていることが本質的な正しさの証明にはならないという反証です。
天動説というパラダイム
観測する技術の精度が高まって天動説では説明のつかないことが出てきたため、結局は天動説は地動説に道を譲ります。
きっかけ、変則的事例。
変則的事例を認識することが変革へのきっかけになります。逆に変則的事例を無視すれば変革は期待できません。
人が動く対価
お金で動く人や人間関係のしがらみで動く人、恩返しで動く人もいるでしょう。結局は対価を求めて動いていることになるのでしょうが、それでも自分で納得できる対価で動きたいものです。
パラダイムというゆりかご
パラダイムは一つであることが望まれます。パラダイムは理解の総体であり、それ一つで全ての事象に説明が付けられると期待されています。逆にパラダイムで説明できない事象は不可解なものとして困惑とともに放置されます。不可解な事象にまともに取り合うとパラダイムそのものが壊れかねないためです。パラダイムを信奉することはの心の安泰をもたらします。しかしその安泰を不快と感じる時、人は従来信じてきたパラダイムを抜け出して新たなパラダイムへと飛び込んでいきます
科学を保護する
伝統 vs 革命
伝統的科学は新発見をつぶしにかかります。科学は新発見よりも既存のパラダイムの保護と育成を優先します。
二つのパラダイム
パラダイムが同時に二つ存在したとしても、それらはぶつかり合うことはありません。お互いに共通するものがないため、否定も肯定もできません。二つのパラダイムは二つの異なる世界です。
信者の絶滅で
ある時代のパラダイムが次のパラダイムに移行するには、前の時代のパラダイムの中に生きた人々が絶滅した時です。地動説が受け入れられたのは、発表から一世紀が過ぎたころでした。
科学が主役
科学は本来、自然の従者です。しかし科学は理論どおりに自然が活動していることを証明しようとします。人間が科学を介して自然を克服できるかのような、傲慢に満ちた幻想が広がります。
とってつけた科学
科学は壮大なストーリーではありません。現実を説明するためにその時その時に取り付けられた主張です。科学自体が進化しているのであって、科学には不備がたくさん内包されています。その改善や変化が科学の進化です。
真理という仮説
我々が真理だと今信じているものは、真理という名前を借りた仮説にすぎません。より真理に近い仮説が生まれるまでの間の、いわば暫定チャンピオンです。
自由と苦しみ
苦しさから逃げるほど行くところがなくなって自由もなくなります。逆に自分から苦しさを求めることで自由が広がります。自分の意志で苦しさに向き合う限りは何度でも苦しむことができます。それが強さを生み、その強さが自由を生みます。
言い訳の瞬発力
何か都合の悪いことが起きた瞬間、自分のせいじゃないという理由を探しいることに気づきました。自分が傷つかないための自己欺瞞でも瞬時に完成させる能力は、。現実を遠ざける技術であり、閉塞感を高めてしまう手段です。
真理という名のパラダイム
今真理だと思っているものはたいてい真理ではなく、のちに間違いであることがわかるということがほどんどです。遠い昔から真理であり続けたことが一体いくつあるでしょう。世間一般に言う真理とは、その時代のパラダイムにすぎません。
29『弁神論』(1710)
「神の善性」「人間の自由」「悪の起源」の三つの小論文からなる著書。
著者紹介

ライプニッツ
- ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ
- Gottfried Wilhelm Leibniz
- 1646年7月1日(グレゴリオ暦)/6月21日(ユリウス暦) – 1716年11月14日
- ドイツの哲学者、数学者。
- ライプツィヒ出身。
- 近世の大陸合理主義を代表する哲学者
- 主著は、『モナドロジー』、『形而上学叙説』、『人間知性新論』、『神義論』など。
- 哲学、数学、科学など幅広い分野で活躍
- 学者・思想家、政治家であり、外交官でもあった。
- 17世紀の様々な学問(法学、政治学、歴史学、神学、哲学、数学、経済学、自然哲学(物理学)、論理学等)を統一し、体系化しようとした。
- 法典改革、モナド論、微積分法、微分記号、積分記号の考案、論理計算の創始、ベルリン科学アカデミーの創設等、多岐にわたる。
最善の世界とは
悪が存在する最善の世界、といえば漫画の舞台設定のようなものですが、これを現実に当てはめるのは難しいでしょう。現実に存在する悪は現実の人間に対して害を与えることになるので、そこを考慮すれば最善とは言えないでしょう。しかし悪の無い世界は影の無い世界のようなもので、一時的一面的ににありえたとしても継続的多面的にはあり得ないでしょう。そう考えると、最善とはやはりいくらかの悪を内包した世界ということになるはずです。
完全という不完全
完全とは不足がないことですが、不足がないことは完全なのでしょうか。不足があって初めて完全なのかもしれません。なぜなら完全には不足が欠けているからです。
悪が善を生む
善が悪を生み、逆に悪が善を生むということもあるでしょう。善ばかりが存在することは悪が生まれる温床になりえますし、その逆もまた真なりでしょう。
楽天的世界観
ライプニッツは世界が神の意志で作られた最善の世界であると主張し、これを他の知識人の多くは楽天的すぎると批判しました。神がを作った世界だから悪の存在すら神の意志であり善の一部という思想は、万人受けしないのは当然です。
因果関係を決めつける
人間は出来事を因果関係として理解しようとしますが、その因果関係を理解する能力は持ち合わせておらず、想像に任せた理解というより決めつけに近いものです。
良い原因を作れ
因果関係が理解できないからといって、何もできないわけではありません。想像にはなりますが、こうすれば将来役に立つだろうということを今しておけば良いのです。自分を何かに縛り付ける必要はありませんが、今できる何か良さそうなことに自分の力を注いでそれを将来の自分や他人の役に立てることは人間にとっての生きる意味や価値になるでしょう。
汎、pan-
- pan-の音訳字。全の意。「汎米主義」。
- 「pan」は、ギリシャ語で「すべての~」を意味する連結要素の接頭語
- 「全~」や「凡~の」、「総~」などの意味になる。
- 「「pantheon(万神殿、全ての神々)」
- 「panacea(万能薬、解決策)」
- 「panorama(全景、パノラマ、概観)」
- 「pan‐pacific(汎太平洋の、太平洋地域全体の)」
- 「panto(全てを) + mimos(まねる人)」という語源を持つ「pantomime(パントマイム、無言劇)」。
- 「pandemic (パンデミック)」は、「pan-(すべての) + demos(人々)」を語源に持ち、世界中で流行する感染症の意味となる。
30『人間知性論』(1689)
ヒュームに思想的な土台を与えた著作。
著者紹介

(注:矢部浩之さんではありません。)
ジョン・ロック
- イギリスの哲学者。
- イギリス経験論の父
- 主著『人間悟性論』(『人間知性論』)において経験論的認識論を体系化した。
- 「自由主義の父」政治哲学者。
- 『統治二論(統治論二篇)』などにおける彼の政治思想は名誉革命を理論的に正当化するものとなり、その中で示された社会契約や抵抗権についての考えはアメリカ独立宣言、フランス人権宣言に大きな影響を与えた。
- 生誕 1632年8月29日イングランド王国・サマセット、リントン
- 死没 1704年10月28日(72歳没)イングランド王国・エセックス
- 研究分野 形而上学、認識論、政治哲学、心の哲学、教育哲学、経済学
- タブラ・ラーサ(経験論における白紙の状態)
- 「被統治者の同意に基づいた政府」
- 自然状態:生命の権利
- 自由と財産権(所有property)
- 明晰と精密、率直と的確がその特徴
- 政治学、法学においても、自然権論、社会契約の形成に、経済学においても、古典派経済学の形成に多大な影響力を与えた。
- ニュートンと交流があった。
観念の発生
観は見て何かを思うということで、念は繰り返し思うことです。だから観念とは何かを見て何かを繰り返し思うことになり、つまりは何かの原理を信じているということです。観念が発生するのは知覚するからであり、そこに知性がかけ合わさって知覚が観念へと固まります。観念とは経験から生まれる法則的な信念です。
知性とは
何かを了解できる力量が知性です。もし自分の知性が了解できる範囲を正確に知ることができたなら、人は惑うことなく有益な人生を送れるでしょう。
偽物の知性
本人が意味を理解していない知識を取り扱っているなら、それは偽物の知性を振りかざしていることになります。自分の無知を覆うために了解できていない知識をあがめているだけです。
タブラ・ラサ
人間は真っ白な状態で生まれるとロックは言います。タブラ・ラサは何も書かれていない石板のことで、知識が知覚を通して得られるものだから先天的知識などないということです。
生得的への疑問
ロックは懐疑論者であり、その時代の社会通念やパラダイムを真理そのもではないと否定しているのだと思います。あらかじめ決められた普遍的に正しいものが存在するかのように振る舞うことを否定しているのです。
出自不明なら生得的
生まれ持っての性質と言われるのは、単にいつどうやって身に付いた性質なのかが不明だからです。生まれつきと言われるのはいつ身に付いたか分からないだけです。
権威で不自由
個人が自由ではない理由は、何らかの権威に服従しているからです。権威は真理の上に立つものなので、権威から自由になりたいなら権威の基盤であるその真理を確かめてみることです。世の中の権威のほとんどは人工物であり、不完全を内包しているはずなので真理ではありません。
意識が生命
植物にはあてはまりませんが、人間が生きているかどうかは意識があるかで決まります。意識が失われた時その人は生きているとは言い難く、もしその意識が帰らなくなったとしたら、その人は亡くなったことになるでしょう。体が残っていても意識が消滅するとき人はその人生を終えたことになります。
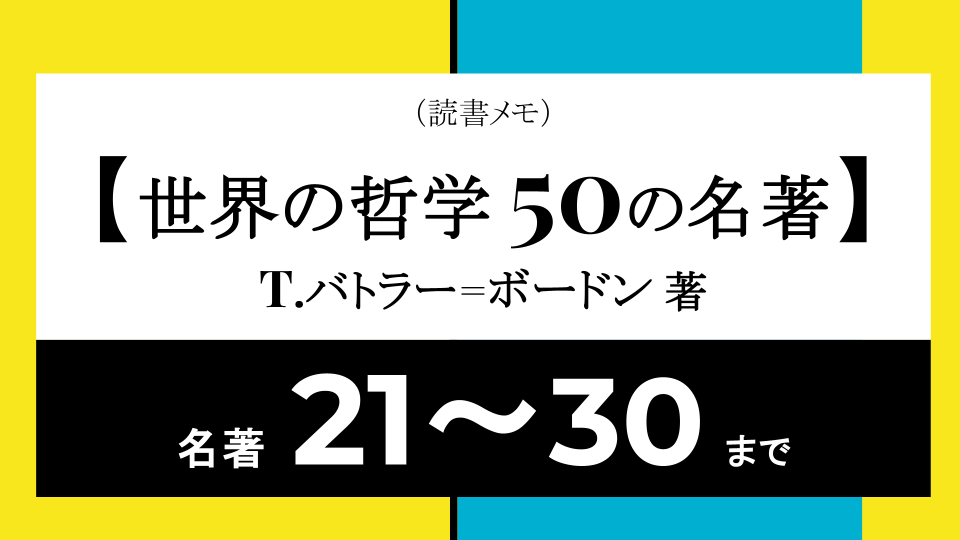
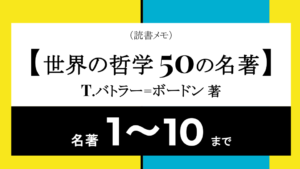
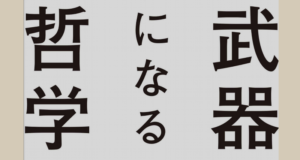
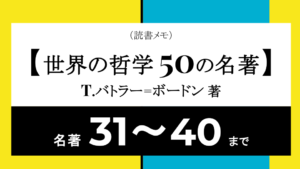
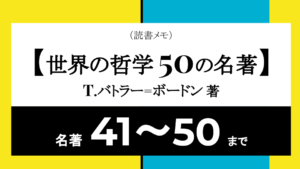
コメント