「結局、人生はアウトプットで決まる 自分の価値を最大化する武器としての勉強術」を読んで学んだことをまとめました。
- 良いアウトプットとは
- アウトプットの改善
- アウトプットとインプットの良い関係とは
- アウトプットの代表格、文章、会話、プレゼンテーションの要点
以上がわかります。著者の中島聡さんは、「Windows95を作った日本人」として有名なプログラマーです。
(おことわり)
・この記事は、記事の作成者が表題の本の内容を参考にアウトプットしたものです。
・表題の本の内容はご自身でご確認ください。
作文がキライ。なぜ?
みんながキライな読書感想文。
学校の読書感想文は、みんなが知るアウトプット経験の代表格です。「文章を書き方」を知らないまま先生が承認するレベルの作文をするのは至難のワザでしょう。それではキライなのも当然です。
でも文章の書き方を知っていれば、書く手間がかかっても褒められる期待が持てます。割に合う作業になるので、文章を嫌う理由はなくなるはずです。
さっそく脱線:ラクな読書感想文の書き方
表題の本を読んで思いついた「ラクな読書感想文の書き方」です。
- 課題図書を眺める。タイトル、序文、目次、本文、あとがき、どこでも。
- 眺めた文で、自分の「想い」が湧く一文を抜き出す。想いとは過去の記憶や体験、いまの連想など。
- 抜き出した一文を書いて、その後に勝手な解釈を述べ、続いて自分の想いを書きつづる。
- 123を繰り返して感想文の長さをかせぐ。
- 感想文の最後に、「以上のことを考えるきっかけを、「(課題図書のタイトル)」からもらうことができました。本に対する興味が以前よりも強くなりました。」としめくくる。
こんなところです。要は「自分の土俵で戦う」ですね。以上、脱線でした。
文章の要点は「正確で簡潔」。
文章とは「情報を伝える道具」。
文章は情報を伝える道具で、必要なのは「正確さと簡潔さ」です。感情や技巧は二の次と言えます。
しかし正確な文章は案外むずかしく、さらに簡潔となるとなおさらです。地道な訓練が必要でしょう。
正確、簡潔な文章の訓練法。
本の中で著者が提案している訓練法が「ランドセルの説明を400字以内で書き、ランドセルを誤解なく理解させよ。ただし読み手はランドセルを全く知らないものとする。」というものです。これは手ごわそうですね。
アウトプットとしての文章。そのチカラ。
文章のチカラは「共有すること」。
文章で知識や経験を他者と共有できます。それも時空をこえて。文章は人類の最大の武器かもしれません。
共有することで未知をも理解できることこそ、文章の魅力でありチカラです。古今東西の知恵が文章を通じて読み手のチカラに変わります。そのチカラを受けて、自分もまた文章を書くことで他者のチカラになれるのです。
インプットした文章から、次のアウトプットへ。
相乗効果で、アウトプットの質を高める。
インプットで知恵を共有して刺激を受けたら、次は自分がアウトプットする番です。
しかしアウトプットする時になって気づくのが、自分の理解の不備な点です
「教えると自分も学べる」は、なぜ?
教えようとして「穴」があることに気づく。
自分の理解が十分だと思っていても、いざ教えてみると理解の不備に気づく。それはよくあることです。気づいたら謙虚な姿勢で学び直しましょう。逆に「学ぶ前提で教える」のもいいかもしれません。
また脱線:教えるときのワザ。
- 自分の理解度が70%の前提で教える。
- のこり30%を後でこっそり学習しておく。
これが教師と生徒、双方の得になるでしょう。何度も脱線してスミマセン。
アウトプットとインプットは両輪。
アウトプットとインプットは補完関係です。単体では完成しません。教えると学ぶ、書くと読む、話すと聞く。料理すると食べる、など、枚挙にいとまがありません。対になって支え合っているのです。
アウトプットが、自分の価値を決める。
読む、書く、読む。このループで文章の価値は磨かれます。
インプットとアウトプットのループです。それが学習であり価値の生産です。
成果とはアウトプットであり、自分の成果はアウトプットで決まる。アウトプットの価値はインプットとの相乗効果で高まるのです。
セルフプロデュースで発信の価値を高める。
自分の興味や強みを理解するほど、発信する内容の質は高まります。自分で自分を上手に売り出すには、自分を客観的に評価しつつ戦略をもって発信することが大切です。
インプットがツライ。なぜ?
好きでなければツライ。それがインプット。
好きなものならいくらでも入ります。しかし嫌いなものは見るのもイヤ、そういうものです。インプットがキライだと思っているとしたら、それはキライなものをインプットしようとしているからです。
インプットがラクになる方法。3選。
- 好きなものだけインプットする。
- インプットのラクな方法を学ぶ。
- インプットの量を最小にする。
1と3は先述の「読書感想文のラクな書き方」と同じです。
2については方法を書いた本が2冊あります。参考にしてみてください。

「好きなこと」とは「しなくてもいいこと」。
好きなことは、しなくてもいいことの中に含まれます。自分の意志でする。したい。その気持ちが好きということなのです。たのまれなくてもすることです。
没頭が価値を生む
本の著者はプログラミングが好きで没頭したから今の充実した人生がある、と言っています。彼に人生の転機が何度かあったようですが、そのたびにプログラミングができる環境を選択し続けてました。
好きなこと、見分け方は?
スティーブジョブズの価値判断の基準が「人生最後の日だとしても、これをするのか?」という自問だといいます。本の著者もこれにならっている判断しているそうです。
好奇心とインプットの関係。
興味がなければインプットも浅くなります。まずは自分の興味を掘り起し、有用で深いインプットが可能にしましょう。
信頼は価値。
本の著者は、信頼は価値あるものだと言います。お金にも劣らない価値であり、常に積み上げる努力がひつようです。
当事者になろう。
商品を買ったり、実際に参加したり、自分が直接関係した件には自然と深い洞察が得られます。インプットとアウトプットの質が向上するはずです。
「一次情報」の価値。
一次情報は価値が高いのは、得るための労力や時間がかかり、そして純粋だからです。
- 自分で直接体験する。
- 公式の情報を得る。
- 三次情報、二次情報、一次情報と、情報をふるいにかけて、さかのぼる。
一次情報は入手がむずかしいですが、質の高いアウトプットには不可欠です。また一次情報
一次情報なら展開可能。
一次情報にたどり着ければ、逆にそこから持論を展開することが可能になります。自分が信ぴょう性のある二次情報の発信者になれる、記事をかけるということです。これは一次情報をつかんだ人の権利であり、二次、三次情報からでは信ぴょう性の薄い、ただのウワサになってしまいます。
個人の発信が、個人への評価を生む。
集団に埋没すると、個人の評価はありえません。自分を評価してもらいたければ、自分で発信するしかありません。努力と結果で自然と認められる、というのは残念ながら甘い考えでしょう。
- 実名で発信し、発信に責任を持つ。
- 発信は、期待を最小にして行う。
- 事実だけでなく、仮説や持論でも良い。
- 発信を継続する。
以上が注意点です。特に実名は大切です。匿名にすれば批判されにくい代わりに評価もされません。欧米では実名の発信が一般的ですが、日本は匿名が一般的です。実名を明かすタイミングは後でもいいかもしれませんが、評価を求めるなら実名公開は早いほうがいいでしょう。
アウトプットその他。会話とプレゼンテーション。
会話はアウトプットの応酬。
会話の一種の発信であり、アウトプットです。会話はキャッチボールとも言われ、共通の興味が必要です。興味がなければ相手はボールを投げ返してくれないでしょう。
相手の興味と自分の興味が合致したとき会話は弾みます。であれば、
- 自分の興味を「カード」として持つ。事前準備でも現地調達でもよい。
- 互いにのカードを相手に見せ合い、合致するものを探す。
- たとえ双方全てのカードが不発に終わっても、その間は会話が続く。
これを日常のいろんな場面で繰り返していけば、会話の経験値と興味のカードも増えるでしょう。会話はアウトプットとアウトプットの応酬とも言えるのではないでしょうか。
プレゼンテーションはクチが命。
本の著者は、「大事なことは自分の口で言う。プレゼン資料に書いてはいけない」と言います。それではプレゼン資料を見た人が「何だこれは。説明しろ」という思うでしょうが、それこそネライだとか。
いかに聴衆に耳を向けさせ、自分の口で伝えるか。それがプレゼンテーションの要点です。プレゼンテーションの命は発表者の言葉なのです。
プレゼンテーション後の質疑応答。その重要性。
すべての作品は受け手の反応が発信者に返ってはじめて完成する、と言えるかもしれません。プレゼンテーションも完成するには聴衆の反応が必要です。プレゼンテーションの質疑応答はプレゼンテーションの価値を証明するものの一つとして大切にすべきです。
未来を予測するよりも、実現する。
本の著者は冒頭で、パソコンの父、アラン・ケイの言葉を引用しています。
「未来は予測するものではなく、実現するものだ。」
日本語にどう訳すかは意見が分かれるかもしれません。私なりの解釈がこれであり、納得できます。
未来を正確に予測はできないし、できても意味はないかもしれません。望む未来が来るならその未来を守る必要があるし、来ないなら生み出す必要があるからです。どの道、じっとはしていられません。
時間×情熱×有効性でアウトプットし、望む未来を生み出しましょう。
この記事を最後まで読んで頂き、ありがとうございました。



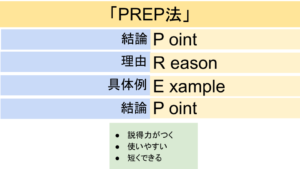

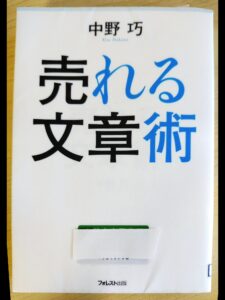
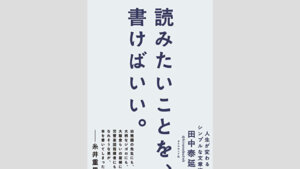

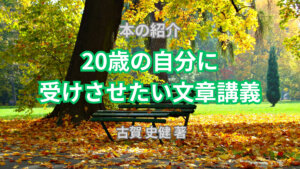
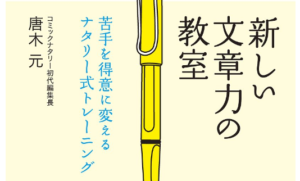
コメント